
ガルージン大使:目指すものは「最後の銃声が響いた翌朝の平和条約ではない」
世界で初めてとなるコロナウイルス・ワクチン「スプートニクV」を開発したロシア。イギリスの医学誌である『ランセット』にその有効性を示す論文が掲載された他、アストラゼネカ社との間でワクチンの併用に関する共同研究が進むなど、 巷間云われているより国際的評価は高い。各国が「ワクチン外交」を繰り広げるなか、「ロシアの戦略はいかなるものなのか。」「コロナウイルスと新しい生活様式という世界の変化の中でロシアの国内政治はどう変化するのか。」また、「日本との関係は、どの様 に発展するのか。」ガルージン駐日大使にお話を伺った。(聞き手:安本浩祥)
※本記事は2021年4月30日時点の情報に基づきます。(『インスピリッツ』本誌11号掲載)
※インタビューはロシア語で実施したものを、日本語訳でまとめたものです。
―「スプートニクV」とアストラゼネカ社のワクチンとの併用が日本でも話題になりましたが、この共同研究を提案したのはロシア側でしょうか、それともイギリス側でしょうか。
ロシアでは、「ロシア直接投資ファンド (RDIF)」がワクチンの生産や技術移管に関する幅広い国際協力を推進しています。昨年12月、RDIFからアストラゼネカ社に対して、ワクチンの併用についての共同研究を提案しました。アストラゼネカ社は、その提案を受け入れ、RDIFとの間で合意が結ばれました。この共同研究が良い成果を生むことを期待したいと思います。
―日本では、国産ワクチンの開発が遅れていますが、ロシアから日本に対する協力提案はあったのでしょうか。
日本の製薬業界の高い研究水準を持ってすれば、国産ワクチンの開発は必ずできると思います。
ロシアからの協力提案ということで云 いますと、他の国々に対して提案しているのと同様に ロシアは、日本での現地生産を行う準備があります。まずは、公式ルートとして日本の厚生労働省に対して提案を行いました。あくまでも私の感覚ですが 日本政府は、ロシアとの協力を端から否定するつもりはないと思います。
実際の協力に向けては、企業との具体的な話し合いになりますから、関心を抱いてくれる日本企業が現れることを期待しています。
―日本政府は、まだ「スプートニクV」を承認していません。何らかの政治的意図はあるのでしょうか。
日本政府がどのような理由でロシアのワクチンを承認していないのか、私は分かりません。おそらくロシアと日本との間で、現地生産などに関する具体的な協力が始まっていないからだと思います。
「何らかの政治的要因があるのかどうか。」 これは、分かりません。私がここで何か言うと 余計な憶測を呼ぶことも考えられますから、それは避けたいと思います。
「なぜ今に至るまでロシアのワクチンが承認されていないのか。」 正確な理由は日本政府がご存じであるはずです。
―ロシアにおいて他の国のワクチンは承認されているのでしょうか。
海外製のワクチンをロシア国内で承認することについて、いくつかの国から要望を受けています。ロシアの然るべき手続きに沿って検討を進めています。この様な問題を政治化することはあってはなりませんし、純粋な科学技術協力、経済協力と云 ったものを政治問題と結びつけてはならないと考えています。
他方アメリカやヨーロッパの西側では、経済問題というものをしばしば政治問題と結びつけることがあります。貿易や学術交流と云ったものにも(政治的理由から)制限を設けることがあります。例えばアメリカとEUは、米露 関係および欧露 関係の対話をすべてストップさせてしまいました。ロシアは、常に脅かされこじつけの理由によって制裁措置を受けています。ワクチン分野においてこの様なことがあってはなりません。
―つまりアメリカがワクチン問題を政治問題にしてしまう恐れもあるということですね。
少なくともこの分野においては、アメリカ政府も良識をもってくれることを願っています。
―国際的なワクチン差別と云う様な状況もあり得ますが、それを回避するための国際的枠組みと云うものはあるのでしょうか。
品質の高いワクチンを入手することが難しい発展途上国にとっては、特に重要な問題です。ロシアは、全ての国がワクチンを平等に入手できることを支持しています。まずは、十分な量の備蓄の確保を目指していますが、そのためには幅広い国際協力が必要です。
ロシアは、2月の国連安保理において、ワクチンを供給するために「全ての軍事行動を一時停止することを求める決議」の共同作成者になりました。また昨年3月に開かれたG20緊急サミットにおいて、プーチン大統領は、「グリーン回廊」の創設を呼びかけました。これは、民間人がただでさえ困難な状況に置かれている紛争地域や内戦地域において、コロナウイルス対策で必要な医薬品や医療行為を提供するためのものです。
ロシアの呼びかけは残念ながら、すべての国によって聞き入れられたわけではありません。国連事務総長がコロナウイルスに関連して、すべての軍事行動の停止を呼びかけた時にも、すべての国がそれに従ったわけではありません。
コロナウイルスによる脅威が存在するにもかかわらず、アメリカは好戦的な態度、他国の内政に干渉する態度を続けています。国連事務総総長の呼びかけにも応じず、ロシアの呼びかけにも応じていません。
興味深いのは、そのような国際的な呼びかけに応じていない国々が、普段は、人権や自由、民主主義の擁護といった「黄金のスタンダード」を自負する国々であるということです。普段から言っていることと、いざこの状況になってやっていることととの間に大きな矛盾があるのです。
―日本ではコロナウイルスの水際対策として入国管理が厳しくなっています。
日本における外国人の入国制限はかなり厳格なものとなっています。これは日本政府の主権的な判断ですから私としてコメントすることではありませんが、外交官として大使館の業務への影響を考えたり、在日ロシア人への情報発信という点では、常に念頭に置いています。
入国管理の問題については、国と国とのつながり、人と人とのつながりが途切れない様にしながら、感染対策の問題と両立させなくてはなりません。そのためには、多国間協力が重要でありそのなかで、各国が主権的な判断をすることになると思います。
―「スプートニクV」は、一回の接種が10ドル以下という安価なものですね。
そうですね。この様な価格面においても、必要とする国々が必要な量を確保するのに役立つと考えています。一回の接種が10ドル以下で通常は、二回の接種で十分とされています。
しかし、ロシア製ワクチンの強みは、価格だけではなくその品質にあると考えています。例えば、保管の面での強みは、冷凍の場合でマイナス18℃ですが乾燥パウダーの状態であれば、2℃から8℃で済みます。
この様な品質の面でも多くの国によって評価されることを期待しています。
―なぜその様な価格が実現できたのでしょうか。補助金などの後押しがあったのでしょうか。
おそらく価格に影響するさまざまな要因が絡んでいるのだと思いますが、詳しい正確なことは、把握していません。ロシアは、ワクチンを広く普及させるために努力しており、これもその成果の一つだと思います。
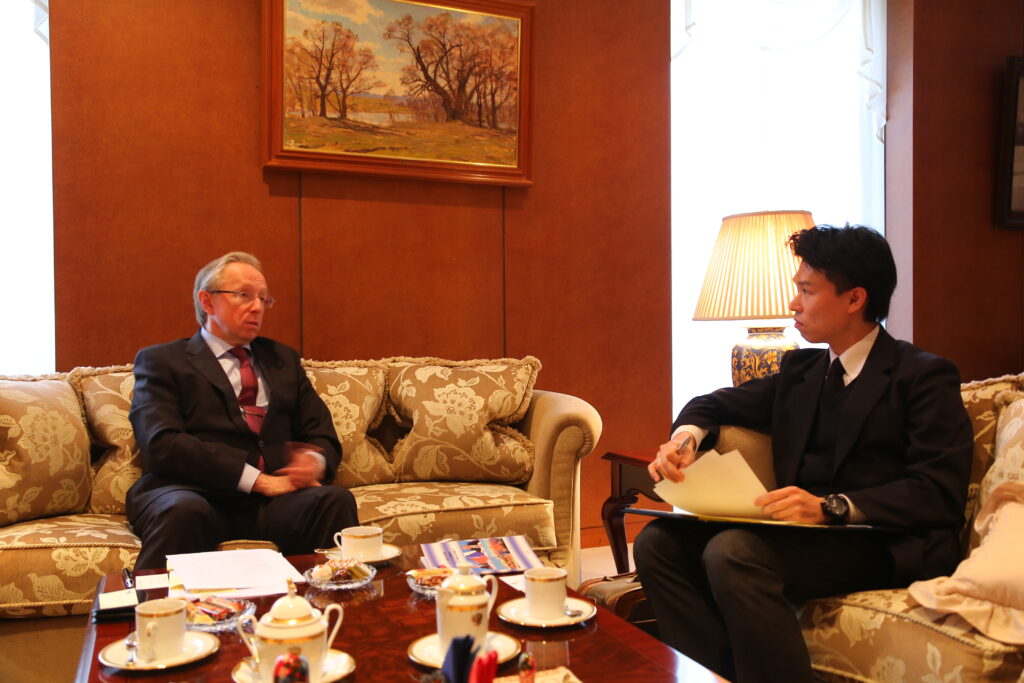
ロシアの国内情勢
モスクワ中心部のルビャンカ広場では、ソ連崩壊の最中にフェリックス・ジェルジンスキー像が撤去されて以来、花壇が設置されているだけの状態が続いている。ここにジェルジンスキー像を戻すか、それとも新しい像を建てるか。対抗馬として出てきたのが「氷上の戦い」で知られるアレクサンドル・ネフスキーだ。2月25日にオンライン投票が実施され、結果はネフスキーが55%、ジェルジンスキーが45%だった。
―ルビャンカ広場の銅像をめぐる問題ですが、ジェルジンスキーの人気がここまで根強いというのは何なのでしょうか。ノスタルジーでしょうか。
この質問には、「ロシア国内の情勢が不安定なのではないか。」 と云う裏の意味が込められている気がしますが、まずもってお答えするならば、「ロシアの政治経済は、安定している。」と言うことです。
コロナウイルスによるロシアのGDPの落ち込みは、それほど大きくありませんでした。他方、アメリカ国内の社会情勢は、不安定化しています。日本は、アメリカの最も近しい同盟国の一つですが、その日本の研究者でさえ、アメリカ社会の分裂を指摘しているのです。アメリカでは、1月6日のデモ参加者に対して武器が使用され4名が亡くなるという事件が起こりました。
コロナウイルスが経済に影響を及ぼすことは当然のことで、それは、政治、社会における緊張も高めることになります。しかしロシアにおいては、アメリカの様な社会分裂は見られません。
「ルビャンカ広場に誰の銅像を建てるのか。」という問題についても、何らかの社会的な不安定を巡る問題ではありませんし、社会的な対立ということでもありません。
この問題を説明するためには、ロシアと云う国家の形成過程を振り返る必要があります。ロシアという国家は、古代ルーシ、ピョートル改革、ロシア帝国、ソビエト連邦、ロシア連邦と各段階を経て発展してきました。その何世紀にも渡る歴史の中で ロシアは、広く知られた人気のある政治家や軍人を輩出してきました。彼らは、様々な社会階級の出身者です。アレクサンドル・ネフスキーもその一人で、13世紀のロシアを守った人物です。
フェリックス・ジェルジンスキーは、1926年に亡くなりましたが、ソ連という国家の形成に大きく貢献しました。そのソ連という国は、15年後、ナチス・ドイツとの戦いにおいて決定的な役割を果たします。ナチズムと云 うのを壊滅する決定的な役割を果たします。そのソ連創業の元勲の一人であるジェルジンスキーが今に至るまで人気が あることはうなずけることです。
投票の結果で言いますと、モスクワ市長の判断は、正しいものだと思います。ネフスキーが得票では少し上回りましたが、ジェルジンスキーの得票も多かったということを受けて市長は、この意見表明の機会が社会における政治対立にならない様に、政治家として正しい判断を行いました。つまり広場は、現状維持というわけです。
―個人的にはどちらに投票したと思いますか。
私はいま公人の立場で話していますから、個人的意見を言う資格は持ち合わせていません。
日露関係の今後
―日露関係においては、1956年の日ソ共同宣言で明確に示されている通り、平和条約の締結がなくては進展しないことは自明の ことです。しかし日本では、どうしても2島返還であったり、4島返還であったりと云う議論が先行します。平和条約の締結より先に島を巡る議論が先行してしまう日本の状況についてどうお考えですか。
その点については、まずその様な議論をしている日本の方々に訊いてみなくてはなりません。彼らがどの様な意図や目的でその様な議論をしているのか、ということです。
ロシアは、今まで繰り返し平和条約交渉を進めるための合理的な提案を行ってきました。私も参加した2018年の東方経済フォーラムにおいては、プーチン大統領が前提条件なしに平和条約を締結することを提案しましたが… 日本には日本の立場があるのでしょう。 残念ながらそれは実現に至りませんでした。
2018年11月には、プーチン大統領と安倍首相とのシンガポール合意があり、1956年のソ連と日本との共同宣言に基づいて平和条約交渉を加速させることで合意しました。
ここで読者の皆さんに2つの点を思い出していただきたいと思います。まず第一に、共同宣言の第一条にある目的の部分です。そこでは1)戦争状態の終結 2)善隣友好関係の樹立 3)外交関係の再開が謳われています。この共同宣言は、両国によって批准された法的な文書であり、今日の露日関係の基礎になっています。正常な善隣友好関係の樹立が謳 われており、幸いなことに 65年の間、概ねその様な方向で両国の関係が発展してきました。
第二に共同宣言では、平和条約の締結において小クリル群島について触れられています。この文書は、古い時代のものなのでシコタンやハボマイという名称が使われています。
質問にもあった通り、私たちは、まず持って平和条約の締結交渉を行っています。しかし、目指すべきものは、単なる平和条約ではありません。繰り返しますが、戦争状態はすでに終結し和平はすでに確立されています。1956年の共同宣言により、両国の戦争状態は終結しました。日本の同盟国がいくら押し付けようとしても、ロシアと日本の間に軍事的対立はないのです。
ですから平和条約とは言っても、ラヴロフ外相がいみじくも指摘している通り、「最後の銃声が響いた翌朝」の様な条約ではないのです。最後の銃声が響いたのはもう70年以上も前のことです。両国の関係はそれ以来とても良い関係が続いています。
私たちが締結しようと考えているのは、単なる平和条約ではなく、より幅広い包括的な協力に関する条約です。ロシアと日本が65年にわたって蓄積してきたポジティブな経験、相互尊重に基づく相互協力の経験を生かしたものになるでしょう。
例えば最近の例だけを挙げてみても、日本が対露 経済制裁に参加したことによる貿易額の減少は、再び増加傾向にありますし、安全保障分野における対話も 防衛大臣と外務大臣を含めた「2+2」という形で新しい段階を迎えています。アフガニスタンの麻薬流通の阻止という点では、アフガニスタン国内にしっかりとした対策機関を創設することで両国は協力しています。経済分野においても、マツダがウラジオストクでエンジンを生産し、それを日本で使うという様な、生産チェーンの新しい試みが見られます。
また文化面においても、コロナで多くのイベントが延期とはなっていますが、ロシア日本交流年をはじめ、地域交流姉妹都市年もあります。毎年、日本では、ロシア文化フェスティバルが開催されロシアにおいても同様です。
両国関係は、とても良好なのです。ですからこれから結ぼうとする平和条約においても、その様な経験を生かして更にその経験を発展させていく様な内容にしなくてはなりません。他にも両国が関心を抱く問題があれば、平和条約の締結後に追加的に議論すればよいのです。
日本では、2島や4島といった議論がなぜあるのかという質問にお答えするならば、おそらくその答えはあなたもご存知でしょう。残念ながら、いま世界で一般的に受け入れられている第二次世界大戦の結果を、日本が受け入れていないところがあるのです。この問題は、日本のパートナーの皆さんにとって非常に繊細な問題と承知していますが、私たちは、客観的かつ冷静に状況を判断しなくてはなりません。
ソ連は、アメリカとイギリスと云う同盟国と共にナチス・ドイツに対して断固として戦いました。日本はイタリアとともに、残念ながら、ナチス・ドイツの同盟国でした。この構図こそが、ソ連、アメリカ、イギリス、そしてフランス、中国という連合国が日本に対してとった行動を決定付けているのです。これは、今日の日本ではなく、あくまでも当時の日本に対してと云うことですが、連合国のとった行動は、その後の国連憲章にも反映されています。
最近、ある日本の同僚と話しているなかで 彼は、どうしてロシアは日本を批判するのかと訊いてきました。「日本は、確かにドイツの同盟国ではあったものの、ホロコーストの様なナチスが行った野蛮な行動はしていないじゃないか。」と言うのです。しかし日本は、ホロコーストを行った国の同盟国でした。同じことなのです。ナチスは、ホロコーストのみならず、スラヴ諸民族の絶滅と云う野蛮な考え方も持っていました。当時の日本は、これに異議を唱えることなく、逆に同盟関係を結んだわけです。非常に残念なことです。
ですから 戦争の終結と共に日本は、然るべき結果に直面することになりました。日本は、その様 なソ連の感情も理解しなくてはなりません。2600万人の戦死者を出し、国家資源の3分の1を失い、ヨーロッパ部の国土が灰燼に帰したのです。これは、とても大きな喪失であり それを忘れることはできません。
一方で私たちは、南クリルに関する日本社会の感情も理解しようと努めています。ですから、かつて日本の領土であった南クリルについては、ビザなし訪問やお墓参り、ロシア領海における日本漁船の操業などの 措置をとっています。
私たちは、日本社会にある感情を理解しようとしています。ですから日本の皆さんにも、私たちの感情を理解しようとしていただきたいと思っています。
―紆余曲折を経て、いまだ全 ての問題が解決していないなかで、日本とロシアの関係が良好であることは、考えようによっては驚くべきことのようにも思えますね。
ロシアと日本は、同盟国ではありませんが、日本と同盟国であるアメリカとその同盟諸国との間には、多くの問題があります。ロシアと日本との関係は、全体としてとても良い関係にありますが、一部で問題も抱えているのは、自然なことだと思います。
日本とアメリカの同盟関係は、同盟自体が問題ということではありません。それは、日本政府の主権的な選択であるわけですから、私たちもその選択を尊重しています。一方でアメリカは、ロシアに対して敵対的な態度を取り続けています。整理すれば、「ロシアは日本と良い関係を築いている。」、「その日本はアメリカとの同盟関係を持っている。」、「そしてアメリカは、ロシアを敵国として、あるいは少なくとも脅威として見ている。」とこうなります。ラヴロフ外相が指摘する通り私たちの関係は、非常に特異なケースだと言えます。ロシアと日本との関係は、第二次世界大戦をめぐる問題を抱えているものの、全体としては良好です。ロシアと日本は、隣国ですからお互いに良いパートナーであることを運命づけられています。競争者や対立者ではありません。まさにその様な日本との関係を私たちは、支持しています。いずれにしても 歴史的な問題は、現代の関係に悪影響を与えてはならないと思います。
ミハイル・ユーリエヴィッチ・ガルージン
駐日ロシア連邦特命全権大使。1960年6月14日モスクワ、ソビエト連邦生まれ。1983年モスクワ国立大学付属アジア・アフリカ諸国大学卒業。1983年外務省入省。1983-1986年、駐日ソ連大使館職員。1992-1997年、駐日ロシア大使館職員。2001-2008年、駐日ロシア大使館公使。2008-2012年、ロシア外務省第三アジア局長。2012-2017年、駐インドネシアロシア大使。2018年1月~、駐日ロシア連邦特命全権大使。2016年ロシア友好勲章受章。

